50代になると親の介護を意識しはじめる年代ですよね。
・仕事との両立ってどうすれば…
・ストレスがつらい…
・施設選びって何を基準に?
と、悩みや不安は尽きません。
この記事では、18年間の在宅介護を経験してきた僕の視点から、
をお届けします。
50代は親の介護を意識するタイミング

50代ともなると、親の年齢は80歳前後の人が多いのではないでしょうか。
そうなると介護を意識するタイミングが増えてきます。
健康診断や異変がきっかけに

50代になると自分自身の体調だけでなく、親の健康状態にも敏感になり始めます。
きっかけ
きっかけとして多いのは、親の健康診断の結果です。
・血糖値が高い
・心臓に異常が見つかった
など、数値として見える変化は不安を一気に現実化させます。
また普段の会話や行動にも、介護の必要性を感じるサインがあります。
- 同じ話を繰り返す
- 趣味への興味がなくなる
- 電話での声が弱々しくなる
- 外出を億劫がる
こうした些細な変化が積み重なった時、
と意識し始める人が多いのです。
早めに行動することが大切
特に50代は、自分の子育てや仕事に手一杯で親の変化を見逃しやすい時期。
「まだ大丈夫だろう」と後回しにしがちですが、少しでも違和感を覚えたら早めに行動することが大切です。
早期に介護の準備を始めることで、心の負担も軽減できます。
- かかりつけ医を決めておく
- 地域包括支援センターに相談する
- 介護保険の申請を検討する
これらは、「まだ元気なうち」だからこそスムーズに進めやすいのです。
親の健康診断や、普段のちょっとした変化。
その一つひとつが、未来の介護を考える「サイン」になり得ます。
- まずは話を聞いてみる
- 情報収集を始める
それが50代のあなたにできる、最初の一歩です。
将来の資金計画から考える

親の介護は、身体的・精神的な負担だけでなく経済的負担も避けては通れません。
50代のうちに介護を意識し始める人の中には、「老後資金の準備」をきっかけに考えるケースも増えています。
介護資金の準備
特に多いのが、以下のような不安です。
・自分たちの老後資金は大丈夫か?
・親の介護費用はどこから捻出すべき?
・施設入所になった場合いくらかかるのか?
介護費用は、在宅介護と施設介護で大きく異なります。
在宅介護では月数万円から10万円程度ですが、施設に入所する場合は月20万~30万円以上かかるケースも珍しくありません。
さらに医療費やリフォーム費用などが加われば、年間100万円以上の出費も想定しておく必要があります。
50代になったら、
・親の年金額預
・貯金の有無
・兄弟姉妹の協力体制
などを早めに把握することが重要です。
親が元気なうちに、
と話し合っておけば、いざという時の混乱を防げます。
自分たちの老後資金の準備
自分たちの老後資金を守るためにも、介護保険の利用や補助制度の活用を視野に入れておきましょう。
そんな状況を避けるには、早めの資金計画が不可欠です。
資金の話はデリケートな問題ですが、50代というタイミングはまだ親にも自分にも「余力」がある時期。
だからこそ冷静に将来を見つめ、
となります。
親の介護負担を軽減する6つの方法

少しでも親の介護負担を軽減する方法は6つ。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
仕事と介護の両立方法

親の介護問題で1番大きいのは、仕事と介護の両立です。
「介護離職」という言葉があるほど重大な問題です。
時短勤務・介護休暇の活用
50代になると、仕事と親の介護を両立せざるを得ない場面が増えてきます。
特にフルタイムで働く人は、
どうやって時間を確保するか
が大きな課題です。
まず知っておきたいのが、
です。
介護休業制度
家族の介護が必要になった場合、
です。
この期間は原則として無給ですが「介護休業給付金」が支給されるため、収入の一部を確保しながら介護に専念できます。
介護休暇制度(年5日~10日)
介護休暇は、介護を理由に1日単位または半日単位で取得できる休暇です。
有給か無給かは会社によりますが、比較的気軽に使いやすく通院の付き添いや急な対応に役立ちます。
介護のための短時間勤務制度
時短勤務制度を使えば、1日最大2時間までの短縮が可能です。
これにより、朝夕の介護時間を確保しつつ仕事も続けられる柔軟な働き方が実現します。
制度利用の注意点
・会社によって運用ルールが異なる(申請期限・取得回数など)
・介護対象となる家族の範囲に制限がある
制度を使ったことが理由で不当な扱いを受けた場合、労基署や専門機関への相談を
実践的なポイント
制度を利用する際は、まず上司や人事に早めに相談することが肝心です。
事前に、
・どんな介護が必要か
・どのくらいの期間サポートが必要か
を整理し具体的に伝えることで、会社側もスムーズに対応しやすくなります。
また制度に頼りすぎず、以下のような工夫も重要です。
・必要に応じて業務の優先順位を見直す
・同僚への業務引き継ぎを早めに行う
・仕事の効率化ツールを活用する(スケジュールアプリなど)
介護と仕事の両立は、
です。
「全部自分で抱え込まない」ことを意識し、使える制度はどんどん活用しましょう。
在宅勤務や副業での調整術
最近は、在宅勤務や副業を活用して介護と仕事を両立する人も増えています。
特にコロナ禍以降テレワークの普及が進み、柔軟な働き方が現実的になりました。
在宅勤務という選択肢
在宅勤務にはこのようなメリットがあります。
- 移動時間ゼロで介護の合間に仕事ができる
- 緊急時にもすぐに対応できる
- 生活リズムを自分で調整しやすい
例えば、
・午前中に仕事
・午後は親の通院付き添い
・夜に再度業務
といった柔軟なスケジュールも可能です。
介護の「隙間時間」を仕事に活かすことで、精神的な負担も軽くなります。
副業・フリーランスという選択肢
正社員としての働き方に限らず、副業やフリーランスも選択肢の一つです。
50代から、
・Webライター
・オンライン講師
・ハンドメイド販売
などの在宅副業を始める人も増えています。
- 場所や時間に縛られにくい
- 小さく始めて徐々に収入を増やせる
- 本業に影響を与えずに収入源を確保できる
副業はすぐに大きな収入には繋がりませんが、
として育てておく価値は大きいです。
在宅勤務・副業での注意点
・仕事と介護の境目が曖昧になりやすい
・介護の負担が大きいと集中力が低下する
・疲労をため込みすぎないよう意識的な休息が必要
在宅勤務や副業は、介護との両立に有効な手段です。
ただし、
適度に外部サービス(デイサービス、訪問介護など)も取り入れ、心身のバランスを整えることが大切です。
実践のコツ
・在宅勤務でも「仕事時間」と「介護時間」をきっちり分ける
・タスク管理ツールを活用する
・「週に一度は介護を休む日」を作る
介護と仕事の両立に正解はありません。
今は、
・制度
・在宅勤務
・副業
と、多様な選択肢があります。
まずは自分に合った方法を試し、小さな成功体験を積み重ねることが長く続けるコツです。

介護ストレスとメンタルケア

介護のストレスはかなりのものです。
僕も在宅介護をしていたので、介護の辛さは身に染みて分かります。
介護うつ・燃え尽き症候群の兆候
介護は、想像以上に心の負担が大きいものです。
特に50代は「仕事」「家庭」「自分の健康」と多くの責任を抱えているため、知らず知らずのうちにストレスが蓄積しやすくなります。
そのまま放置すると、
に陥るリスクがあります。
介護うつの主な兆候
・気分の落ち込みが続く
・朝起きるのがつらい
・動きたくない
・物事への興味、関心が薄れる
・食欲不振
・体重減少
・不眠、または過眠
・焦りや不安感が強まる
・些細なことで怒りっぽくなる
これらの症状は、最初は「疲れているだけ」と思いがちですが、数週間続くようなら要注意です。
特に、
といったネガティブ思考が出てきた場合は、早めに医療機関を受診するべきです。
燃え尽き症候群の特徴
・これまでできていたことが急にできなくなる
・何もかもどうでもいいと感じる
・感情が麻痺し無気力になる
・介護に対して罪悪感を抱きやすくなる
燃え尽き症候群は「頑張りすぎる人」が陥りやすい状態です。
真面目で責任感が強い人ほど「自分が頑張らなきゃ」と抱え込み、限界を超えてしまいます。
兆候を感じたらすぐにすべきこと
・休息を優先する(数日だけでも可)
・周囲に「つらい」と打ち明ける
・市区町村の介護相談窓口に連絡する
・医療機関(心療内科・精神科)に相談する
介護うつや燃え尽き症候群は、誰でも起こり得る心の不調です。
と捉え、早めの対処を心がけましょう。
サポートを求めるコツ
介護を一人で抱え込まないためには、
サポートを求める力がとても重要
です。
特に50代は「自分でなんとかしなければ」と考えてしまい、なかなか周囲に頼れない人も少なくありません。
ここでは、
をご紹介します。
まずは身近な人に現状を話す
最初の一歩は、
ことです。
「大変そうだね」と言われたら、「実はこんな状況で…」と具体的に説明しましょう。
話すだけでも心が軽くなり、意外なところで「手伝うよ」と言ってくれる人が現れることもあります。
兄弟姉妹には役割を分担してもらう
介護は「自分だけの問題ではない」と意識することが大切です。
兄弟姉妹がいる場合は、役割を明確にして分担しましょう。
- 金銭面は長男が管理する
- 通院の付き添いは次男が担当する
- 手続き関係は長女が引き受ける
「誰がどこまで責任を持つか」を具体的に決めることで、トラブルを防ぎ精神的な負担も軽くなります。
行政サービス・介護サービスを積極活用
行政の介護サービスは「使えるものは全部使う」くらいの気持ちでOKです。
- 地域包括支援センターでの相談
- 介護保険サービス(デイサービス・訪問介護など)
- ショートステイ(短期入所)での一時休息
- 介護タクシーや配食サービスの利用
地域包括支援センターは無料で利用でき、介護保険の申請やサービスの紹介も行ってくれます。
SOSは恥ではないと意識する
介護は長期戦です。
自分一人で抱え込めば、共倒れになるリスクが高まります。
上手に頼ることこそが介護のスキルです。
あなたの負担を減らすことは、親にとってもプラスになります。
で、積極的にサポートを求めましょう。
施設選びのポイント

介護施設と一口に言っても、種類はさまざまです。
施設選びのポイントを上げていきます。
介護施設の種類で選ぶ
・特養(特別養護老人ホーム)
・老健(介護老人保健施設)
・有料老人ホーム
は、よく検討される3つの選択肢です。
それぞれの特徴を理解しておくことで、親の状態や家計に合った施設選びがしやすくなります。
特別養護老人ホーム(特養)
- 公的施設で費用が安め(月5~15万円程度)
- 原則、要介護3以上の方が入所可能
- 長期間の入所が前提(終身利用も可)
- 経済的負担が少なく済む
- 介護サービスが充実しており安心感が高い
- 入所待ちが長い(数ヶ月~数年のことも)
- 入居対象が要介護3以上に限られる
介護老人保健施設(老健)
- 医療ケアを受けながらリハビリができる施設
- 在宅復帰を目的とした中間的な施設
- 入所期間は原則3~6ヶ月程度
- 医師が常駐しており医療体制が充実
- リハビリを集中的に受けられる
- 長期間の入所はできない
- 退所後の住まいを事前に考える必要がある
有料老人ホーム
- 民間企業が運営する施設で自由度が高い
- 介護付き・住宅型・自立型など種類が豊富
- 入居一時金が必要な場合も多い
- サービス内容が多彩で選択肢が多い
- 比較的入居しやすい
- 費用が高額(月15万~30万円以上が一般的)
- 施設ごとに質やサービスに大きな差がある
施設選びの基本は「目的の明確化」
施設を選ぶ際は、以下をまず整理しましょう。
・長期間入所が必要か
・短期間のリハビリか
・費用はどのくらい負担できるか
・医療的ケアはどこまで必要か
「なんとなく」で選ぶと、入所後に後悔することも多いため必ず目的を明確にすることが大切です。
見学・チェックリスト&注意点
施設を選ぶときは、必ず「現地見学」が必須です。
パンフレットやホームページだけでは、実際の雰囲気や職員の対応まではわかりません。
見学時のチェックポイント
以下のリストをもとに、必ず現地で確認しましょう。
- 清潔感はあるか(ニオイもチェック)
- 共用スペースの広さ・明るさ
- 居室の広さ、設備(トイレ・ベッドなど)
- 入浴設備の使いやすさ、安全性
- 挨拶や接客態度は丁寧か
- 入居者に対する声かけやサポートの様子
- 職員の人数(手薄になっていないか)
- 夜間体制の有無
- 介護体制(どの程度サポートしてくれるか)
- 医療連携(看護師・医師の常駐有無)
- 料金の内訳、追加費用の発生条件
- 食事の内容・アレルギー対応の有無
見学時の注意点
・平日の通常業務時に訪問する(イベント日以外が◎)
・実際に働いている職員と話す(管理職だけでなく)
・できれば入居者とも会話してみる
・複数の施設を見学して比較する
特に「ニオイ」や「職員の自然な対応」は、入居後の生活満足度に直結する重要ポイントです。
見学後は「第一印象」をメモしておき、家族としっかり意見を共有しましょう。
契約時のトラブルを防ぐコツ
・契約書・重要事項説明書は必ず隅々まで読む
・不明点は納得いくまで質問する
・途中解約時の返金条件も必ず確認する
「急いで決めるほど失敗する」と心得て、慎重に選びましょう。
金銭的負担の軽減策

介護でかかる費用は、結構馬鹿になりません。
介護にどのくらいの費用がかかるのか、また補助金や助成金などの制度を知ることも重要なポイントです。
介護保険制度の基本と自己負担額
介護の現実的な悩みとして、多くの人が最初に直面するのが
です。
介護には想像以上にお金がかかりますが、日本には介護保険制度という公的な支援があります。
介護保険制度の基本
介護保険制度は、40歳以上のすべての人が保険料を支払い介護が必要になったときに利用できる制度です。
対象者は、以下の2つのグループに分かれます。
・第1号被保険者:65歳以上の高齢者
→ 原因を問わず、要介護・要支援の認定を受ければ利用可能
・第2号被保険者:40歳~64歳の人
→ 特定疾病(がん・脳血管疾患など16種類)が原因の場合に利用可能
介護認定を受けると利用できる
介護保険サービスを使うには、「要介護認定」を受ける必要があります。
認定は要支援1・2、要介護1~5の7段階に分かれ、介護の必要度に応じて使えるサービスや金額の上限が決まります。
自己負担額は原則1割~3割
介護保険サービスの自己負担額は、所得に応じて1~3割です。
- 一般的な年金受給者:1割負担
- 現役並み所得者(年収約280万円以上):2割または3割負担
例えば、
で済みます。
利用できる主なサービス
・訪問介護(ヘルパー派遣)
・デイサービス(通所介護)
・ショートステイ(短期入所)
・介護用ベッドや手すりのレンタル
・特別養護老人ホームの利用
など
費用の上限を超えた場合は「高額介護サービス費制度」
介護サービスの利用額が一定の上限を超えると、高額介護サービス費として超過分が払い戻されます。
これにより、低所得者でも安心してサービスを利用できる仕組みです。
早めの申請・準備がカギ
介護保険制度は、手続きをしなければ使えません。
「まだ早いかな」と思わず、
できます。
補助金・助成金・税制優遇制度
介護費用をさらに抑えるためには、介護保険だけでなく
も積極的に活用しましょう。
住宅改修費の助成制度(介護保険内)
介護保険では、自宅のバリアフリー化のための住宅改修費を、
- 手すりの設置
- 段差解消(スロープ設置など)
- 滑り防止の床材変更
- ドアの引き戸化
- トイレの洋式化
など
福祉用具購入費の助成(介護保険内)
入浴用イスやポータブルトイレなど、福祉用具の購入にも年10万円まで助成されます(自己負担1~3割)。
所得税・住民税の控除(医療費控除・障害者控除など)
介護費用の一部は、医療費控除の対象となります。
対象になるケースは限られますが、次のような費用は控除可能です。
- 医師の指示による訪問看護費用
- 介護保険サービスのうち、医療行為に準ずるもの
また、親が障害者手帳を持っている場合は障害者控除も使え、所得税・住民税の軽減が可能です。
地方自治体の独自助成
自治体によっては、さらに独自の助成金や補助金を設けていることがあります。
- 家事代行サービスの費用補助
- 介護タクシー利用料の補助
- 配食サービスの料金助成
手続きの窓口は「地域包括支援センター」
これらの制度を利用するには、地域包括支援センターに相談するのが最も確実です。
申請書の書き方や必要書類の準備もサポートしてもらえるため、活用しない手はありません。
制度は「調べた者勝ち」
介護に関する補助金・助成金は、地域差が大きく情報が埋もれがちです。
インターネットで調べるだけでなく、
です。
50代からはじめる親の終活準備
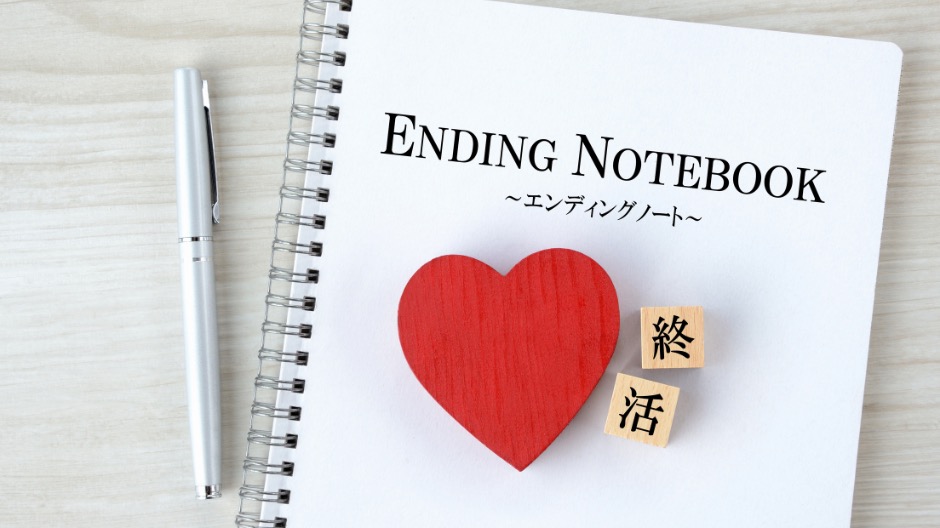

終活というとまだ早いのでは?
と感じてしまうかもしれませんが、親も自分も同じく歳をとっています。
まだ話せる元気なうちに準備をしておくと、
エンディングノートの活用方法
介護の問題を考えるとき、避けて通れないのが「終活」です。
50代は、親も高齢期に差しかかり元気なうちに「これからのこと」を話し合える貴重な時期です。
そんな終活の第一歩としておすすめなのが、エンディングノートの活用です。
エンディングノートとは?
人生の終わりに向けての希望や情報をまとめておくノートです。
法的効力はありませんが、万一の時に家族が困らないようにするための大切な準備です。
- 本人の基本情報(氏名・生年月日・保険証番号など)
- 医療や介護についての希望
- 延命治療の可否
- 介護施設への入所の意向
- 財産の情報(銀行口座・不動産・保険など)
- 葬儀やお墓の希望
- 親しい友人や知人の連絡先
- 家族へのメッセージ
- いざという時、家族がスムーズに対応できる
- 親の意向を尊重しやすくなる
- 相続トラブルの予防になる
- 親自身の安心感が高まる
書く時のポイント
・一度に全て書こうとせず少しずつ進める
・家族で会話しながら笑顔で取り組む
・定期的に見直し更新する(年1回が目安)
50代からの始め方



最近、終活ってよく聞くけどエンディングノートって知ってる?
このように、
です。
エンディングノートは書店・ネット通販・市販のテンプレートでも簡単に手に入ります。
無理強いはNG
無理に書かせようとすると、親はかえって拒否反応を示します。
・書きたいことだけでいいよ
・元気なうちに準備しておくと安心だよ
と優しく促しましょう。
相続・遺言・お金の話し合い
エンディングノートとあわせて、
です。
特に50代は、親の介護や施設費用が具体的に現実化する年代。
早めに話し合っておかないと、「相続トラブル」が発生するリスクも高まります。
話し合いの主なテーマ
・財産の内容(現金・不動産・預貯金・株式など)
・借金・ローンの有無
・介護費用をどう分担するか
・相続税の有無・納税資金の準備
・遺言書の有無・作成の意向
相続トラブルを防ぐには「見える化」が重要
財産の見える化(リスト化)をするだけでも、家族間のもめごとは格段に減ります。
- 銀行口座番号と残高
- 所有する不動産の詳細
- 保険の契約内容
- 借金やローンの有無と金額
遺言書の種類とポイント
遺言書は、法的効力がある唯一の意思表示です。
- 自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
- 公正証書遺言(公証役場で作成)
- 秘密証書遺言(あまり使われない)
特に、
です。
費用は数万円~数十万円程度ですが、確実性を重視するなら検討の価値は大いにあります。
話し合いの進め方
・きっかけは「老後資金」や「介護の話」から自然に切り出す
・親だけでなく兄弟姉妹とも必ず共有する
・専門家(司法書士・税理士・弁護士)への相談も早めに検討する
「揉めない家族」の共通点
・情報をオープンに共有している
・相続の意思決定に親の意向を最優先している
・定期的に集まって進捗を確認している
相続やお金の話は気が重く感じがちですが、
です。
親自身も、



子どもたちに迷惑をかけたくない
と思っているケースは多いので、「家族のための安心材料」として少しずつ話を進めましょう。
家族・地域との連携術


介護は1人で抱え込むと、どんどん悪い方向へと流れていきます。
家族や地域の協力は強い味方になります。
兄弟・親族との役割分担
介護は、家族の協力なしには乗り越えられない場面が多々あります。
特に兄弟や親族との役割分担は、精神的・金銭的な負担を軽くするための大切なステップです。
役割分担は「最初」が肝心
介護が始まったばかりの頃は、「自分がやればいい」と抱え込みがちです。
しかし長期戦になることを考え、最初の段階で家族会議を開くことが重要です。
- 誰がどの役割を担当するか(介護・金銭・手続き)
- 各自の得意・不得意を踏まえた分担
- 緊急時の対応方法
- 必要なら専門家を交えた相談も視野に入れる
役割分担の具体例
| 役割 | 担当者の例 |
|---|---|
| 金銭管理 | 長男 |
| 通院付き添い | 次女 |
| 介護サービス手配 | 次男 |
| 行政手続き | 長女 |
ため、無理なく続けられる形にすることがポイントです。
トラブルを防ぐコツ
・誰が一番苦労しているかを競わない
・必ず定期的に情報共有する(LINEグループなども有効)
・必要なら外部の専門家を交えて公平性を保つ
・「できないことはできない」と正直に伝える
兄弟間の温度差はつきものですが、
ことが、長続きの秘訣です。
地域包括支援センター・ケアマネの利用
介護は家族だけで抱え込まず、地域の支援機関を活用することも非常に大切です。
中心的な役割を果たすのが、
です。
地域包括支援センターとは?
市区町村が設置する公的機関で、介護に関するあらゆる相談に対応してくれます。
利用は無料で、誰でも気軽に相談可能です。
- 介護保険の申請サポート
- 介護サービスの紹介
- 福祉用具や住宅改修の相談
- 認知症や虐待などの専門相談
- 家族のメンタルケア支援
ケアマネジャー(介護支援専門員)の役割
ケアマネジャーは、
です。
要介護認定を受けた後、ケアプラン(介護計画書)を作成し必要なサービスを手配してくれます。
- 介護保険サービスの調整・手続き
- 家族の希望を踏まえたケアプラン作成
- 介護事業者との橋渡し
- サービス利用中の状況把握・見直し
地域包括支援センター+ケアマネ=最強の組み合わせ
地域包括支援センターは、ケアマネジャー選びの相談窓口にもなります。
まずはセンターに相談し、自分たちに合ったケアマネを紹介してもらうのが安心です。
うまく活用するコツ
・遠慮せず困っていることを具体的に伝える
・「こんなこと相談していいの?」と思わず気軽に頼る
・定期的に連絡を取り信頼関係を築く
相談は“早め早め”がカギ
です。
介護の課題は早めに動くことで、精神的にも金銭的にも負担を軽減できます。
まとめ


50代で直面する親の介護は、誰にとっても大きな悩みです。
・介護保険制度
・行政サービス
・家族の協力
を上手に活用すれば、負担は大きく減らせます。
大切なのは、
という意識です。
早めの準備と家族・地域との連携が、親も自分も安心できる未来につながります。
「自分だけで抱え込まない介護」を、今日から意識してみましょう。
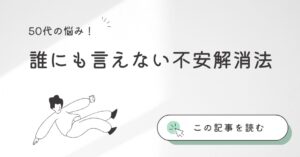
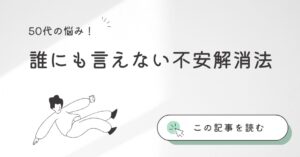




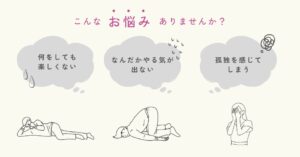
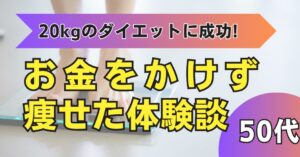
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] あわせて読みたい 50代で出てくる悩み「親の介護問題」!負担を軽減する6つの方法 50代になると親の介護を意識しはじめる年代ですよね。 ・仕事との両立ってどうすれば…・ス […]
[…] 50代で出てくる悩み「親の介護問題」!負担を軽減する6つの方法 2025年7月15日 […]